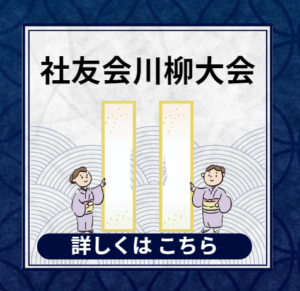爽やかな秋晴れの2025年10月30日、「歴史探訪 歩こう会 ~堺の魅力発見~鉄砲鍛冶屋敷、刃物と千利休、与謝野晶子の足跡を訪ねて」が58名の社友参加のもと挙行された。今回は関西に居ながら「堺市」を訪問したことがない会員が多く、本企画を募集したところ、直ぐ募集人員60名に達した。2名キャンセルがあったものの、58名が6班に分かれて行動。各施設に全員が一度に入れない為、集合場所を3班ごとに2か所(ザビエル公園と南海電鉄七道駅)に分けて、6名の地元ガイドさんにお世話になった。
まず鉄砲鍛冶屋敷を訪れる途中で堺が「環濠都市」と呼ばれ、安土桃山時代には豪商を中心とした自由都市の防御機能を有していた歴史の説明を受けた。その壕(ほり)の一部は今も残っている。
1543年ポルトガルから種子島に火縄銃が伝来した。島主・種子島時尭(ときたか)は鉄炮2丁をポルトガル人から購入し臣下に国産化を命じた。これを聞きつけた堺の商人・橘屋又三郎はすぐさま種子島を訪れて製法を学び、堺で作るようになった。堺には古墳時代から鍬(くわ)や鋤(すき)などの鉄製品をつくってきた蓄積があった。堺での鉄砲量産は以降の戦いの在り方を大きく変えていった。私たちは日本で唯一現存する江戸時代の「鉄砲鍛冶屋敷」(井上関右衛門家住宅)を訪れた。鞴(ふいご)を使い、鉄を鍛えて「銃身」に仕上げる「鍛冶場」他が再現されている。完成品の火縄銃に触れることは出来ないが、数十本並んでいる銃身を持つと見た目以上にずしりと重く驚く。この鉄を加工する技術はその後、各種包丁を製造する刃物製造業に活かされ、現在でも20軒程の刃物製造/卸業者が存在する。軟鉄の塊から刃物が如何に造られるかよく理解できる施設が「堺伝匠館」で、ここには欧米からお目当ての包丁を買い求めに来るインバウンド客が多く訪れる。

「鉄砲鍛冶屋敷」(井上関右衛門家住宅)

「鉄砲鍛冶屋敷」(井上関右衛門家住宅)
このあと大阪府内で唯一の路面電車(阪堺電車)に乗って移動し、日蓮宗「妙國寺」を訪れた。樹齢1100年の大蘇鉄は信長や家康が愛した。小堀遠州が作庭した蘇鉄の枯山水庭園は家康のお膝元駿府の街を模したものとなっている。多くの参加者が今回初めて耳にした「堺事件」は幕末に堺の街を警護していた土佐藩士が、堺港から上陸して狼藉を働いたフランス水兵11名を斬りつけ、死に至らしめた。フランス側から処罰を求められ、境内で割腹死した同数の土佐藩士を弔う石碑が境内に残されており、辞世の句や遺髪が展示されている。

妙國寺内庭園の奇妙な石

土佐藩士11名切腹の場所(1868年堺事件)

「木曽路」懐石料理の昼食
その後、2グループ全員が合流して「木曽路」にて懐石料理の昼食をとった。
昼食後、約400年前にわび茶を大成させた堺生まれの千利休の屋敷跡を訪問、その門前で集合写真を撮った。時代こそ違うものの堺市が誇る二人の偉人、千利休と与謝野晶子について貴重な資料が多く展示された施設「さかい利晶の杜」は見所満載だった。1階の千利休茶の湯館、2階の与謝野晶子記念館を巡り、最後に1階の展示室でガイドさんから「自由都市・環濠都市」堺の町並みの説明を受けた。明治から昭和にかけ活躍した歌人、与謝野晶子は堺市内の和菓子店「駿河屋」に生まれ、地元で「乱れ髪」や「源氏物語の現代語訳」他多数の作品を生んだ。また、夫・鉄幹と共にパリへ洋行しフランスの芸術家とも交流した。あの時代には珍しい行動派で情熱的な女性であったことが良く分かった。
このあと、希望者は館内で表千家の「立礼呈茶」(りゅうれいていちゃ)に参加。椅子に腰かけて堺の和菓子と薄茶のお点前を経験し解散となった。新しい発見の多かった一日であった。

千利休屋敷跡前 第1~3班

千利休屋敷跡前 第4~6班
参加者から頂いた主な感想は以下:
・阪堺電車に乗ったり、妙国寺の土佐藩士11名の切腹の史実展示に驚いたりと、面白い一日でした。
・堺事件のことは初めて知りました。
・ガイドさんは知識豊富で説明が上手でとても分かりやすかった。
・バラエティに富んだ訪問先でとても勉強になった。食事内容も良く満足しました。
・堺伝匠館から昼食場所までの歩行距離が長かった=>1.1㎞だったがお疲れだったのか…
・初めて参加した方や帰り際の数名から次回も楽しみにしているとメッセージあり。
・今回は各訪問先での滞在時間が短く、改めてまた堺市を訪問したい。