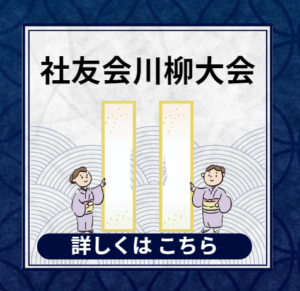好天に恵まれた2025年4月18日、西部社友会「春の歩こう会 ― 歴史探訪 中之島から道修町の街歩き」が50名の社友の参加のもと開催された。
大阪市のど真ん中を流れる堂島川と土佐堀川に挟まれた東西約3㎞の中州の中之島。この地域の開発は大坂屈指の豪商である淀屋常安により1615年に始まり、江戸時代には諸藩の蔵屋敷が立ち並び、全国各地の物資が集まる「天下の台所」と称せられ、1730年に米の中央市場である堂島米市場が設置された。これは世界初の先物取引市場と言われ、のちの大阪株取引所の起源と言われている。明治になると、諸藩の蔵屋敷は払い下げられ、商業の中心として金融業も発展、さらに国の重要文化財の大阪府立図書館や大阪府立中央公会堂等の文化施設や大阪帝国大学をはじめとする学校や病院が企業、市民の寄付などで建設され、近代商都大阪の情報と文化の発信地となった。中之島の東側対岸の北浜にある大阪取引所(旧・大阪証券取引所)は、大阪経済界を牽引した五代友厚が発起人の一人となった大阪株取引所が前身であるレトロな建物の一部が残された近代的なビルに生まれ変わり、ビルの北側正面には五代の銅像が立っている。
午前9時半過ぎ、電光掲示板に各社の株価が映し出される大阪取引所のロビーに参加 者が集合、4班に分かれガイドさんと共に順次出発、先ず五代友厚の銅像の説明から始まり、中之島へ渡る1915年竣工の難波橋の橋詰に鎮座する石造の2対のライオン像建造の背景説明を受けた。
者が集合、4班に分かれガイドさんと共に順次出発、先ず五代友厚の銅像の説明から始まり、中之島へ渡る1915年竣工の難波橋の橋詰に鎮座する石造の2対のライオン像建造の背景説明を受けた。
難波橋を渡り中之島に入る。建築家・安藤忠雄氏が寄贈建設した「こども本の森 中之島」は2020年完成、中庭に「青春」を表す人の背丈程の大きな青りんごが設置されている。その西側に美しく佇む赤煉瓦作りの中央公会堂(重文)は1913年に建てられた新古典主義様式デザインの公共ホールで、講演会やコンサートに利用されている。このあと、府立図書館(重文)、大阪市役所を訪れ、昼食は公会堂の地下にある重厚な雰囲気のレストランで参加者全員が名物料理の牛肉デミグラスソース・オムレツとコーヒーに舌鼓を打った。
昼食後は「適塾」(重文、大阪大学医学部の前身)の内部を見学した。適塾は蘭学・医学研究の第一人者緒方洪庵が当時 多数の死者を出していた天然痘の予防のために1849年、この地に「除痘館」を作り、西日本各地に広めていった。その始まりの地である。門下生に福沢諭吉や大村益次郎らを輩出した学塾の現在は大阪大学が管理している。緒方洪庵記念財団が管理する「除痘館記念資料室」を見学した後、隣接する日本一古い木造建築の大阪市立「愛珠」幼稚園の外観を見学した。同園は1880年創設で、立派な建物ゆえか幼稚園の人気は高く入園倍率は6倍を超え、幼稚園の先生にとっても憧れの職場とのこと。
多数の死者を出していた天然痘の予防のために1849年、この地に「除痘館」を作り、西日本各地に広めていった。その始まりの地である。門下生に福沢諭吉や大村益次郎らを輩出した学塾の現在は大阪大学が管理している。緒方洪庵記念財団が管理する「除痘館記念資料室」を見学した後、隣接する日本一古い木造建築の大阪市立「愛珠」幼稚園の外観を見学した。同園は1880年創設で、立派な建物ゆえか幼稚園の人気は高く入園倍率は6倍を超え、幼稚園の先生にとっても憧れの職場とのこと。
そのあと、道修町(どしょうまち)へ移動。1722年、徳川八代将軍吉宗により薬種商124軒が薬種屋仲間として幕府より公認を受け、道修町は薬種取引の中心となり、今でも製薬メーカーが集積している。中でも資料館を有する4社(田辺三菱製薬、塩野義製薬、武田薬品、住友ファーマ)の資料館及び古来より薬の神様と崇められ、病気平癒・健康増進祈願の少彦名(すくなひこな)神社を訪れた。中でも田辺三菱製薬では社員ガイドの方から、江戸時代に漢方薬の原料を輸入するための御朱印書や戦後は西洋薬主体に切り替え、現在ではリュウマチ薬など得意分野の薬品を病院などへ卸している状況など同社の歴史について約40分間にわたり詳しく説明していただいた。午後4時ごろ、淀屋橋駅で解散となった。参加者から頂いた今回の感想の多くは「身近にあった史蹟と歴史を知る大変有意義な一日であった」。